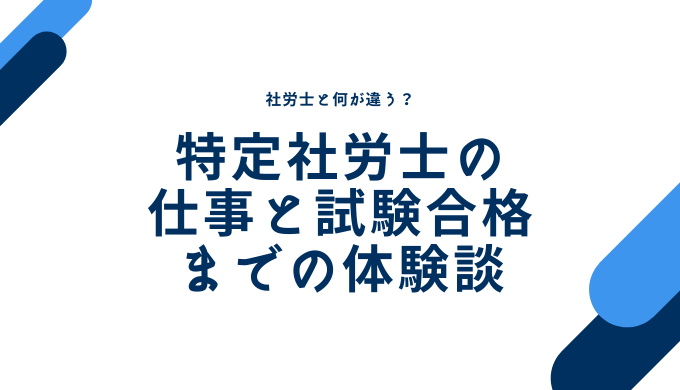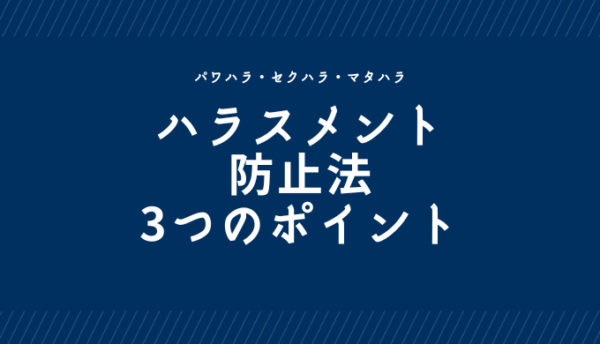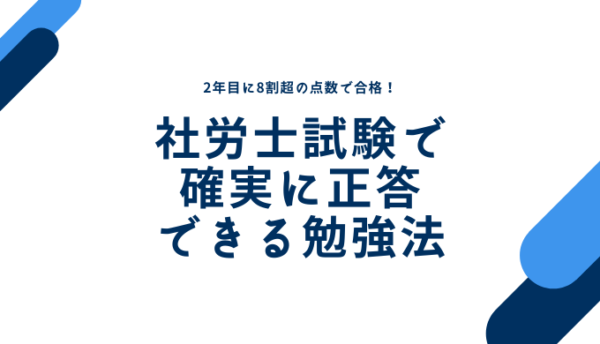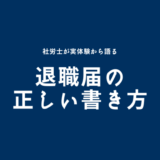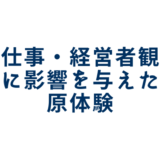社労士のシモデ(@sr_shmd)です。
社会保険労務士(以下「社労士」)が「特定社会保険労務士」になると、できる業務の幅が広がります。
私は社労士試験に合格した翌年に特定社労士の試験を受けて無事に合格しました。
この記事では、特定社労士の仕事と試験内容や試験合格までの体験談を紹介します。

この記事は次のような人にオススメです!
- 特定社労士を目指している人
- 社労士試験を受験中の人
- どの資格を取得しようか迷っている人
特定社労士とは?社労士・弁護士・行政書士との違い
社労士として登録済みの者が「特別研修」を修了して「紛争解決手続代理業務試験」に合格し、社会保険労務士名簿に付記されると「特定社労士」になります。
社労士が特定社労士になると、紛争解決手続代理業務を行えるようになります。
特定社労士ができる紛争解決手続代理業務とは?
社労士が特定社労士になると行える「紛争解決手続代理業務」とは、労働にかかわるトラブルを解決するための裁判外紛争解決手続(ADR)において行う代理業務のことです。
会社と従業員との間で労働条件などに関してトラブルになり、話し合いで解決しない場合は、あっせんや調停などの公的な制度において第三者を介入させて解決を目指すことができます。
特定社労士は、この裁判の手前(裁判外)での解決制度において当事者の代理をすることが可能です。
具体的な業務内容は、以下のようなものです(全国社会保険労務士会連合会ホームページより)。
- 都道府県労働局や都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続等の代理
- 都道府県労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続等の代理
- 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理(単独で代理することができる紛争目的価額の上限は120万円)
- 代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉や和解契約の締結の代理を含む
つまり、退職・解雇、残業代、ハラスメントに関するトラブルなどに関するあっせんや調停手続きの代理を行います。
たとえば、「会社に退職しろと言われた、未払い残業代も含めて〇〇円支払え」とか、「ハラスメント相談をしたが会社がきちんと対応してくれなかった、慰謝料として〇〇円支払え」といったようなトラブルです。
会社と従業員、双方が根拠を基に主張をして、いくらなら支払えるのかという話し合いになります。
こうした話し合いにおいては、退職の意思表示や手続きの瑕疵があるか、慰謝料としてどの程度が相場かなどの知識が必要です。
あっせん・調停とは?
特定社労士が携わる「あっせん」や「調停」とは何なのでしょうか。
まず、「あっせん」とは、労働問題の専門家である委員が仲介となって労働に関するトラブルを解決する制度です。
従業員が各都道府県労働局や全国の労働基準監督署にある「総合労働相談コーナー」などに相談に行くと、あっせんの制度を紹介されることがあります。
特定社労士は、会社や従業員の代理人となってトラブルの経緯を整理した資料を作成したりあっせん当日に当事者の主張を説明したりします。
調停もあっせんと似たような制度です。調停委員会における話し合いによって労働に関するトラブルの解決を目指します。
あっせんと異なる点は、委員の人数と受諾勧告の有無です。
あっせん委員は1名でもOKなのに対し、調停は3名の調停委員による合議制となります。
また、あっせんの和解案には受諾勧告はできませんが、調停案に対しては受諾勧告を行うことができます。
特定社労士と社会保険労務士との違い
上記のような紛争解決手続代理業務を、特定社労士でない社労士は行うことができません。
一方で特定社労士は、まず社労士として登録している者でないと受験できませんので、社労士が行っている業務はすべて行うことができます。
社会保険労務士の独占業務
そもそも社労士は、どのような仕事をしているのでしょうか。
例えば、社労士は以下のような仕事をしています。
- 社会保険・労働保険の手続き
- 給与計算
- 助成金申請
- 年金相談
- 就業規則の作成
- 労務相談
なお社労士の独占業務は、社労士でない方が有償で行うことはできませんが、無償であればできます。
この点は、税理士と異なります。
税理士の業務は、税理士でない方は無償であっても行うことはできないのです。
社会保険労務士試験の試験科目
ちなみに社会保険労務士の試験は、以下の科目で構成されています。
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労災保険法
- 雇用保険法
- 健康保険法
- 国民年金法
- 厚生年金保険法
- 一般常識

社労士試験の勉強法については、以下の記事を参考にしてください
特定社労士と弁護士との違い
では、特定社労士と弁護士とはどのように違うのでしょうか。
特定社労士は裁判外紛争解決手続(ADR)であるあっせんや調停において当事者の代理人を務めることができますが、労働審判や裁判では代理人にはなれません。
労働審判や裁判で代理権を持つのは弁護士だけです。
一方で、弁護士は専門領域が広いため、相談した弁護士が労働問題を専門にしているとは限りません。
労働に関するトラブルで弁護士に相談する場合には、労働問題を専門としている弁護士に依頼することをおすすめします。
特定社労士と行政書士との違い
行政書士は、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成・提出手続を行える資格です。
労働トラブルについてのあっせんや調停の手続きには、行政書士が携わることはできません。
行政書士も専門分野が多岐にわたります。
仕事を依頼する場合には依頼したい業務内容と行政書士の専門分野が合致しているかをよく調べるとよいでしょう。
特定社労士になっても意味がない?年収は上がる?
社労士が特定社労士になったとしても、すぐにあっせんや調停の仕事が舞い込んでくるわけではありません。
そのため、特定社労士になったからといってすぐに年収が上がるわけではないのです。
求人を見ても、社労士を募集している会社はありますが、わざわざ特定に限って募集している会社は見かけたことがありません。
ただ、すぐに年収が上がるわけではなくとも、特定社労士になるための研修や試験勉強の過程で知識量は確実に増えていきます。

受験料や勉強時間にかかるコストと長期的なメリットを比較して、特定社労士の試験を受けるかどうか検討するとよいでしょう
特定社労士になるには
社労士が特定社労士になるには、特別研修を修了して、紛争解決手続代理業務試験に合格し、社労士名簿に合格した旨の付記を受けることが必要です。
社労士として登録している者のみが特別研修を受講できます。
社労士試験の勉強方法については、以下の記事を参考にしてください。
特別研修の申し込み方法は?「月刊社労士」をチェック
特別研修の情報は、毎年6月ごろに全国社会保険労務士会連合会のホームページや『月刊社労士』に掲載されます。
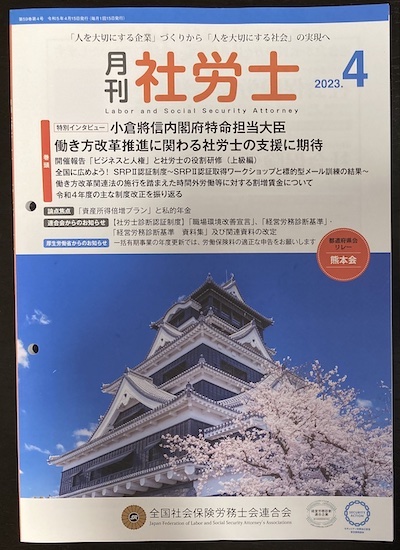
全国社会保険労務士会連合会のホームページにて特別研修の申込要領を請求することが可能です。

特別研修に興味のある社労士の方は毎年6月ごろの月刊社労士をチェックしてみてください
特別研修の概要
特別研修は、総時間数63.5時間のカリキュラムで構成されます。
毎年9月〜11月にかけて開催されています。
第18回(令和4年度)のカリキュラムと日程は、以下の通りでした。
| カリキュラム | 所要時間 | 令和4年度の日程 |
|---|---|---|
| 中央発信講義(eラーニング) | 30.5時間 | 令和4年9月2日(金)〜令和4年9月30日(金) |
| グループ研修 | 18時間 | 令和4年10月1日(土)〜令和4年10月30日(日) |
| ゼミナール | 15時間 | 令和4年11月18日(金)10時〜17時 令和4年11月19日(土)10時〜17時 令和4年11月26日(金)10時〜13時 |
グループ研修とゼミナールは、以下の主要7都市で開催されています。
- 札幌市
- 仙台市
- 東京都中央区
- 名古屋市
- 大阪市
- 広島市
- 福岡市
中央発信講義(30.5時間)
中央発信講義は、憲法を基本とする法体系の中で、個別労働関係法の制度や理論を理解し、また個別労働関係紛争解決手続代理人としての倫理を確立させることを目的として行われます。
私が受験した令和元年度はコロナ禍前でしたので、eラーニングではなく受講生が集まって同じ講義の動画を見る形式でした。
日程が決められており、仕事をしながら土日に受講するのはなかなか大変だったのを覚えています。
第18回(令和4年度)の中央発信講義は以下の通りでした(月刊社労士2022年6月号より)。
- 特定社会保険労務士の果たす役割と職責・・・0.5時間
- 専門家の責任と倫理・・・3時間
- 憲法(基本的人権に係るもの)・・・3時間
- 民法(契約法、不法行為法の基本原則に係るもの)・・・6時間
- 労使関係法・・・3時間
- 労働契約・労働条件・・・8時間 ①労働契約総論(3時間)/②賃金体系と労働条件の変更(2.5時間)/③労働時間・割増賃金等と健康上の安全配慮義務(2.5時間)
- 個別労働関係法制に関する専門知識・・・5時間 ①退職、解雇、雇止め等雇用終了の問題(2.5時間)/男女均等、セクハラ、パワハラ、非正規雇用の問題(2.5時間)
- 個別労働関係紛争解決制度・・・2時間
グループ研修(18時間)
グループ研修は、個別労働関係紛争における書面(申請書・答弁書)の作成に関する研修として行われます。
グループの構成は、特定社労士のリーダー1名と10名程度の受講者です。
グループごとにケーススタディーに関する申請書や答弁書を起案します。
中央発信講義は30.5時間受け身で聞き続けなければならないため辛いものがありましたが、グループ研修は討論をしたり書面を作成したりする能動的な研修で楽しかったです。
私が受講したときの特定社労士のリーダーの先生は丁寧に研修を進めてくれたため、とても勉強になりました。

グループ研修をしっかりと受けることが試験対策になります
ゼミナール(15時間)
ゼミナールは、個別労働関係紛争の代理業務を行う上での実践的な能力を身につけることを目的として行われます。
ケーススタディーを中心に申請書・答弁書の検討、争点整理、和解交渉の技術、代理人の権限と倫理等について学びます。
私が受講したときの講師は弁護士の先生でした。
一人ひとり当てて質疑応答をしていくスタイルでしたので、眠くならずに済みました。
分からないところを最終確認できる大切な時間です。
特別研修の受講費用
特別研修の受講料は、教材代込みで85,000円です(月刊社労士2022年6月号より)。
一定期間は受講申し込みを取り消すことが可能です。
取り消しした場合には受講料の半額が返還されます。
特別研修の修了認定
特別研修を修了するには、研修の全日程に出席してすべてのカリキュラムを受講し、研修内容を充分に理解したと認められ、かつ、起案等の必要とされる課題すべてを定められた期日までに提出することが要件となります(月刊社労士2022年6月号より)。
なお、各講義に15分以上遅刻した場合は出席と認められません。原則として中座も認められません。
また、早退した場合は出席と認められません。

グループ研修とゼミナールの日には確実に予定を空けておくことが必要です
特定社労士の試験対策は?独学でパスできる?
特定社労士になるための紛争解決手続代理業務試験は、独学でパスすることは可能です。
私は過去問を一通り解いて試験に臨みましたが、下表の点数で合格できました。
| 第15回紛争解決手続代理業務試験科目 | 点数 | 合格基準 |
|---|---|---|
| あっせん事例(70点満点) | 46 | 足切りの点数設定なし |
| 倫理規定に関する事例(30点満点) | 13 | 10点以上 |
| 総得点(100点満点) | 59 | 55点以上 |

特別研修をしっかり受けることと過去問を解くことが大切です
紛争解決手続代理業務試験の受験資格
紛争解決手続代理業務試験の受験資格は、社会保険労務士として登録した者が特別研修を修了することによって与えられます。
試験内容・合格基準
紛争解決手続代理業務試験は、記述式の大問2つによって構成されています。
第1問があっせん事例で70点満点、第2問が倫理規定に関する事例で30点満点です。
制限時間は2時間で、特別研修のゼミナール3日目の後に行われます。
合格基準は、100点満点中55点以上、かつ、第2問10点以上と定められています。
受験者数・合格率・難易度
紛争解決手続代理業務試験の難易度は、合格率50〜60%ほどです。
ちなみに第18回(令和4年度)紛争解決手続代理業務試験の合格率は以下の通りでした。
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 901人 | 478人 | 53.1% |
紛争解決手続代理業務試験の受験費用
紛争解決手続代理業務試験の受験料は15,000円です。
特別研修の受講料85,000円、その他旅費や参考書代などを合わせるとかなりの出費となります。

特定社労士を目指すかどうかは、仕事内容や得られる知識の内容とコストを比較して検討するとよいでしょう
紛争解決手続代理業務試験の勉強方法・勉強時間
紛争解決手続代理業務試験においては、あっせんのケーススタディーにおける法的な問題点を指摘したり、倫理的に特定社労士として依頼を受けてよいかなどを検討したりします。
特別研修の中でも、特にグループ研修が重要だと考えます。
グループ研修ではケーススタディーを用いて特定社労士であるリーダーと受講生同士で討論できるため、ここで疑問点を解消しておくことができるからです。
また、多くの方が仕事をしながら受験勉強を行うことと思います。
特別研修のほかに多くの時間を割くことは難しいのではないかと思います。
ただ、この記述式の試験はボールペンでマス目に書いていかなければならない独特なものです。
そのため、過去問が記載されたテキストを購入して一通り解いておくことは必要だと思います。
トータルの勉強時間としては、特別研修63.5時間と過去問36時間(2時間×18年分)の計100時間は最低限確保した方がよいでしょう。

特別研修と過去問の時間を合わせて少なくとも100時間は勉強時間にあてる必要があります
記述式の試験にパスするためのポイント
紛争解決手続代理業務試験の答案用紙はマス目になっており、ボールペンで直接書いていきます。
鉛筆や消しゴムを使うことはできません。
試験までに過去問を解くなどして、ボールペンで文章を書くことに慣れておきましょう。
試験本番では、ボールペンで解答をいきなり書いていくために、問題を読んで構成を考える時間を十分にとることがポイントになると考えます。
なお、修正したい場合は二重線を引いて、マス目の空いているスペースに書いていくことが可能です。
社労士試験の合格率が6〜7%であるのに対し特定社労士試験の合格率は50〜60%なので、緊張感はまるで違います。
ただ、その分試験会場ではあまりやる気のない方も見られるため、「絶対に一発で受かる!」と自分で気合いを入れることが重要です。
そして、実際に裁判外で当事者の代理人として話し合いをするには、出来事の合法・違法性を主張することよりも、何が起きたかを整理して、当事者が何を求めているのかを正しく理解することが大切だと感じています。

答案はボールペンで書くため、解答の構成を考える時間をしっかりとることがポイントだと考えます
紛争解決手続代理業務試験に落ちたら?再受験できる?
紛争解決手続代理業務試験に不合格だった場合には、翌年以降の試験に再チャレンジすることが可能です。
特別講習を一から受講することはできないようですが、中央発信講義とゼミナールは聴講生として参加できるようです。
詳細は、毎年6月頃の月刊社労士をチェックしてみてください。
特定社労士の仕事と試験合格までの体験談まとめ
- 社労士が特定社労士になると紛争解決手続代理業務を行えるようになる
- 特定社労士になるには、特別研修を修了して紛争解決手続代理業務試験に合格し、社労士名簿に合格した旨の付記を受けることが必要
- 特別研修は総時間数63.5時間のカリキュラムで構成され、すべてのカリキュラムに参加しなければならない
- 紛争解決手続代理業務試験にパスするには、特別研修をしっかり受けて過去問を解いて準備し、本番では問題を読んで構成を考える時間を十分にとることがポイントになる