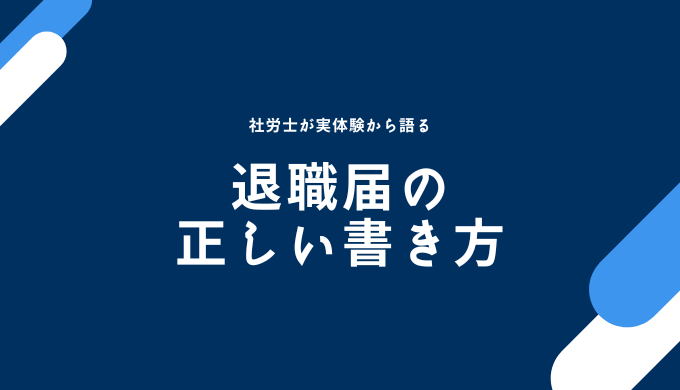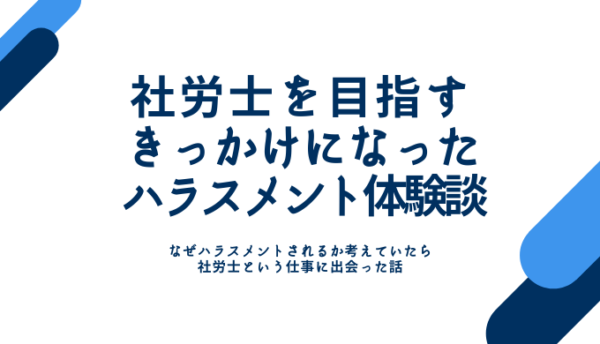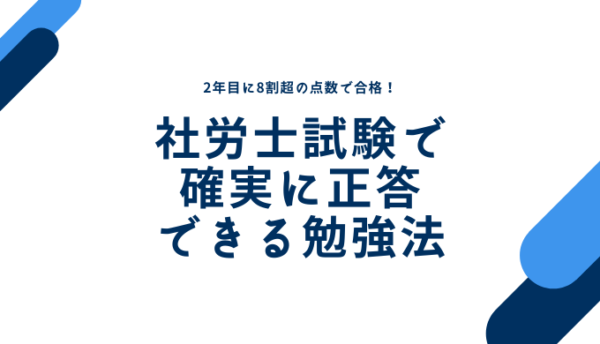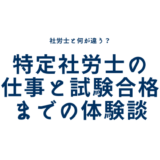社労士のシモデ(@sr_shmd)です。
このブログを始めて半年後の2021年夏、勤務先の社会保険労務士事務所を退職して独立することにしました。
それまで職は転々としていたものの、退職願をきちんと書いて提出したのは初めてのことでした。
この記事では、実体験をもとにした退職届の正しい書き方を解説します。

この記事は次のような人にオススメです!
- シモデのプロフィールに興味がある人
- 退職届の正しい書き方を知りたい人
- 退職や転職をしようかどうか悩んでいる人
目次 非表示
4年半の勤務社労士生活
30歳になる直前で異業種から社労士事務所に転職し、4年半勤めました。
社労士という仕事にたどり着いたのには、さまざまな理由があるのですが、主な出来事は以下の記事にまとめています。
社労士事務所に勤務している間に学校に通わせていただき、社労士資格を取得しました。
4年半の間に以下のような業務を幅広く経験させてもらいました。
- 社会保険関係の手続き
- 給与計算
- 36協定作成
- 就業規則作成
- 労務相談への対応
- 労働組合との団体交渉への参加
- 労働局でのあっせんへの参加
- セミナー運営、資料作成、講師
- ホームページの管理・更新等
- 顧客向け情報提供サイトの立ち上げ・コンテンツ作成・運営等
- 顧客向けニュースレターの記事作成・編集
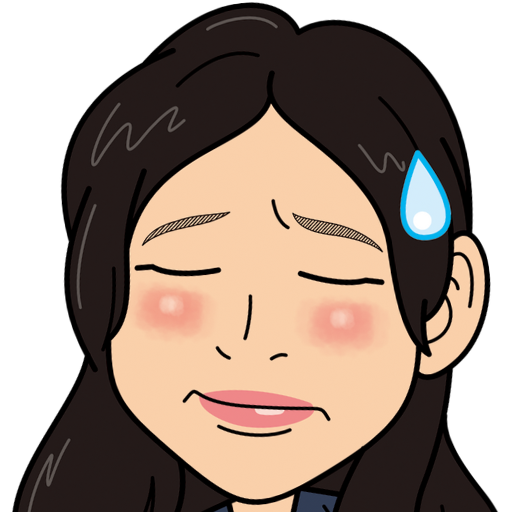
大変お世話になりとても良くしてもらったため退職届を書いて提出するときにはさすがに緊張しました
退職願の正しい書き方
書かないと法律上どうなる?退職届と「退職の意思表示」
さて、ここからが本題です。

会社を辞めよう!
と決めたとき、退職届を絶対に書かなければならないというイメージがあるかもしれません。
しかしながら、法律上は退職届を書かなければ会社を辞められないわけではないのです。
「辞めます」という退職の意思表示が会社に到達すれば、少なくとも2週間で労働契約は終了します。(民法第627条)

退職届は会社を辞めるために法律上必要とされているものではありません
退職の理由と記入例
退職届には何を書かなければならないのでしょうか。
退職届の記載項目についても法律上の定めはありません。
確実に伝えなければならないことは「一体いつ辞める意思があるのか」の1点です。
記入例は以下の通りとなります。
この度、一身上の都合により、勝手ながら、◯年◯月◯日をもって退職いたします。
退職の理由については、正直に書かなければならないわけではありません。
日本では「職業選択の自由」が保障されていますので、会社には正しい理由を問いただす権利はないのです。

退職の理由は「一身上の都合」で十分です
印鑑・封筒は必要?手書きでなきゃダメ?
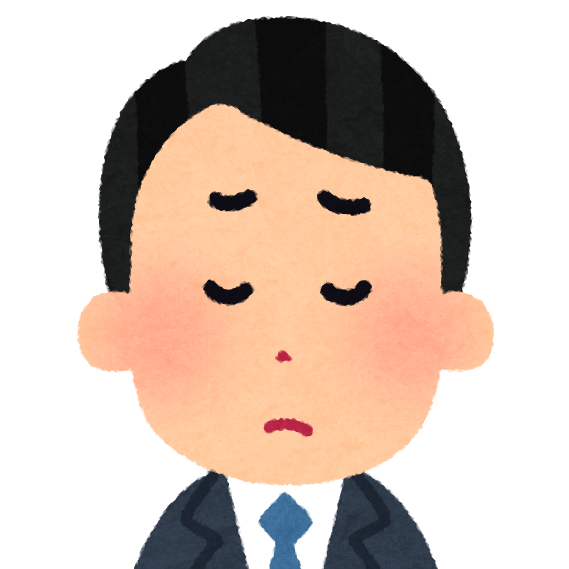
退職届に押印は必要でしょうか?
退職届の書き方に法律上の定めはありませんので、印鑑や封筒がなくても構いません。
また、手書きでなければならないという決まりもありません。
少なくとも、記入した日付と自分の名前は記載しておきましょう。
しかしながら、会社の文化によっては、手書きかつ押印してあった方が「きちんとした文書」という印象になることはあり得ます。
また、封筒を用意する場合は白い封筒が望ましいでしょう。

印鑑・封筒・手書きについては、会社の風土や与えたい印象によって決めるとよいと考えます
メール・郵送・口頭ではダメ?
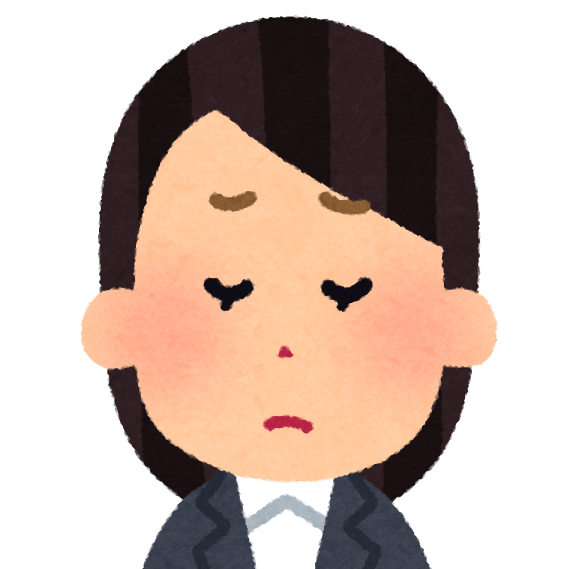
退職届を提出するためには絶対に会社に行かなければならないでしょうか・・・
前述の通り、「辞めます」という退職の意思表示が会社に到達すれば、少なくとも2週間後には会社を辞めることができます。
意思表示の方法には、法律上の定めはありません。
書面で手渡ししなければならないわけではないのです。
そのため、メールや郵送、口頭で伝えても法律上は問題ありません。
しかしながら、確実に退職の意思を伝えるためには書面による手渡しが無難です。
ただし、出社できない等の特別な事情がある場合にはメールや郵送で退職する旨を伝えてもよいでしょう。

書面での提出が一般的ですが、状況に合わせてメール・郵送・口頭で伝える方法を検討しましょう
退職届はいつまでに提出しなければいけない?
通常、就業規則には「自分の意思で退職する場合には◯日前に申し出ること」といった条文が記載されています。
「30日前」と決められているケースが多いです。
民法の「2週間前」と就業規則の「30日前」ではどちらが優先されるのでしょうか。
法律上は、民法の「2週間前」が優先されます。
しかし、トラブルなく穏便に辞めていこうとする場合には、就業規則のルールを守った方が無難でしょう。

今日辞めたいと思っても辞められないのですか?
民法で言うところの「2週間」とは、「少なくとも2週間経てば辞められる」ということです。
したがって、「今日辞めます」といって会社が了承すれば、その日に辞めることは可能です。

特段トラブルがなければ就業規則のルールを守ることが無難でしょう
退職届と退職願の違い
いざ退職届を書こうとしたとき、はたと

退職届と退職願、どちらが正解なのか・・・
とお思いになるかもしれません。
結論から言えば、どちらも正解です。
敢えて違いを言えば、退職届は退職する意思を「伝える」もの、退職願は退職したいと「お願いする」ものです。
そのため、退職願の文面は以下のようになります。
この度、一身上の都合により、勝手ながら、◯年◯月◯日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。
退職届はあくまで「お願い」なので、却下される可能性があることに注意が必要です。

結局使いませんでしたが、私は退職願と退職届の両方を用意し、退職願の受け取りを拒否されたら退職届を提出しようと考えていました
退職届の受け取りを拒否されたら

退職届を受け取ってもらえませんでした・・・
もし会社に退職届の受け取りを拒否されたら、どうすれば良いのでしょうか。
何度かけあっても話にならないようであれば、書面で提出したことを証明する「配達記録付き内容証明郵便」を使う方法があります。
内容証明郵便であれば退職の意思表示が確実に会社に到達するため、そこから少なくとも2週間経てば労働契約は終了します。
退職の手続きをしてくれない、離職票を発行してくれないといった場合には、ハローワークや労働基準監督署に相談してみましょう。
2週間経てば法律上労働契約は終了するため、退職したとして役所の方で手続きを進めてくれます。
退職届を書くよう強要された場合

退職届を書くよう会社に強要されました、書かなければならないのでしょうか
退職届を書くよう強要された場合、応じる必要はありません。
しかし、断りきれずに書いてしまうこともあるかもしれません。
その場合には、退職の意思は本意ではなかったとして撤回することが可能です。
相談先としては都道府県労働局や労働基準監督署に設置されている「総合労働相談コーナー」が挙げられます。
「すぐに相談したい」「まずはちょっと話を聞いてほしい」といったときには、社労士への相談もご検討ください。
直接あなたを救うことはできなくても、一緒にお気持ちを整理してどのような第一歩を踏み出すかを考えます。
セクハラ・パワハラの解決方法を一緒に考えます 現状とお気持ちを整理して、第一歩を踏み出すお手伝いをします
本意ではないのに退職届を書いてしまったとしても取り返しがつかないわけではありません
退職届の正しい書き方のまとめ
- 退職の意思表示が会社に到達すれば、少なくとも2週間で労働契約は終了する
- 退職届には「◯年◯月◯日に辞める」旨を記載する
- 就業規則に記載してあるルールを守り、手書きの書面を手渡しすることが無難
- 退職届の受け取りを拒否されたら「配達記録付き内容証明郵便」を使う方法がある
- 退職届を書くよう強要されたら「総合労働相談コーナー」などに相談しよう