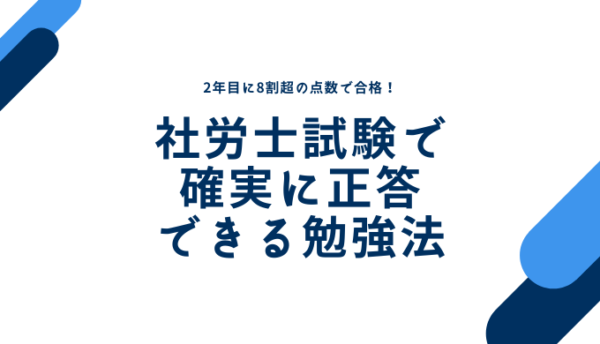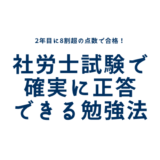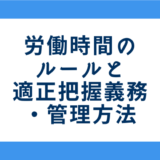社労士のシモデ(@sr_shmd)です。
社労士試験にパスすることを目標にしている間は、合格するための勉強で精一杯なのではないでしょうか。
合格したあとにどのような生活が待っているのか、なかなかイメージがしにくいと思います。
私は、社労士は合格後も勉強をし続けなければならないことを知りませんでした。
知識をアップデートするには、勉強家の仲間を作ったり、積極的に情報収集をしたりし続けることが大切です。
この記事では、社労士試験に合格した後の勉強に使えるおすすめのツールを5つ紹介します。

この記事は次のような人にオススメです!
- 社労士試験に合格したばかりの人
- 社労士試験を受けている人
- 社労士試験を受けようか検討中の人
社労士試験合格後の勉強におすすめの5つのツール
社労士試験のために勉強した知識は基礎として非常に重要です。
しかし、お客さまの質問や要望に的確にこたえていくには、教科書だけでは不十分だと思います。
私が日頃業務を遂行するにあたって使っているおすすめのツールは、次の5つです。
- 社労士会会報・メルマガ
- 菅野和夫先生『労働法』
- 各種資料・雑誌
- 株式会社日本法令「SJS社労士情報サイト」
- 転職サイト「MS Agent」

以下に5つのおすすめ勉強ツールの内容を紹介します
①社労士会会報・メールマガジン
おすすめ勉強ツールの一つ目は、社労士会の会報やメールマガジンです。
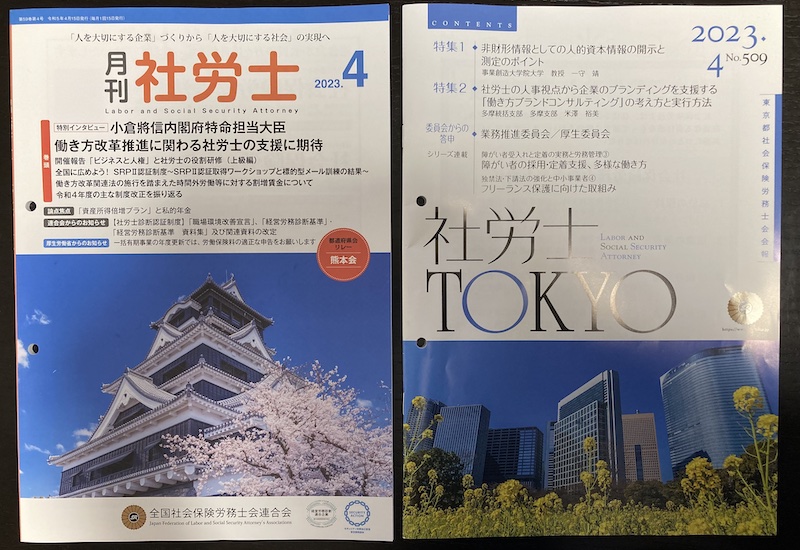
社労士試験の科目の中でも、とくに社会保険関係は法改正が頻繁に行われます。
受験勉強中の情報のままで、知識をアップデートしなければ、お客さまに間違った情報を伝えてしまうかもしれません。
法改正情報を得ないことは、業務において無駄なことをしてしまうことにも繋がります。
たとえば最近、社会保険関係の手続きにおいては、添付資料が不要になったり、署名・押印が不要になったりしました。
こうした最新情報を得ていないと、ルーティーン化している業務においては特に、無駄なことをし続けてしまう可能性があるのです。
主な法改正については、全国社会保険労務士連合会が発行している『月刊社労士』や地区の社会保険労務士会が発行している会報やメルマガでチェックするようにしましょう。

社労士として登録すると会報やメールマガジンで情報を取得できるようになります
②菅野和夫先生『労働法』
社労士として仕事をしていくにあたっては、幅広い専門分野からどの分野に特化するかを決める方が多いと思います。
その分野によって必要な書籍は変わってきます。
ただ、社労士なら誰でも手元に置いておきたい本が一冊あります。
菅野和夫先生の『労働法』です。
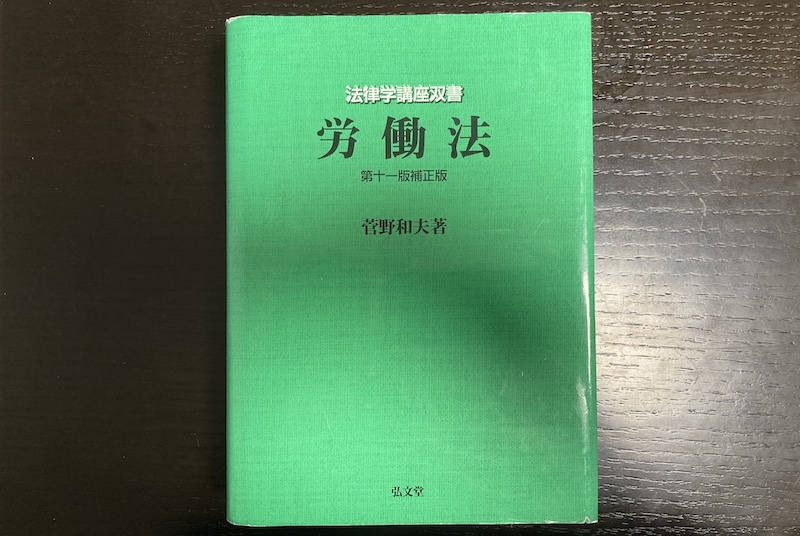
菅野先生は日本の労働法学者で、実務は菅野先生が確立された見解をベースに動いているともいえるそうです。
私は
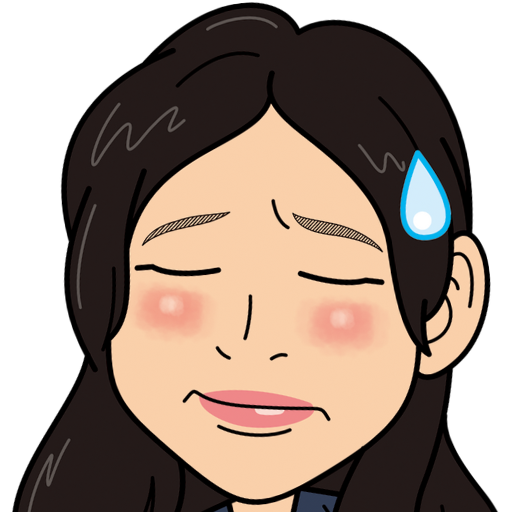
どうしてこの法律が作られたんだっけ・・・?
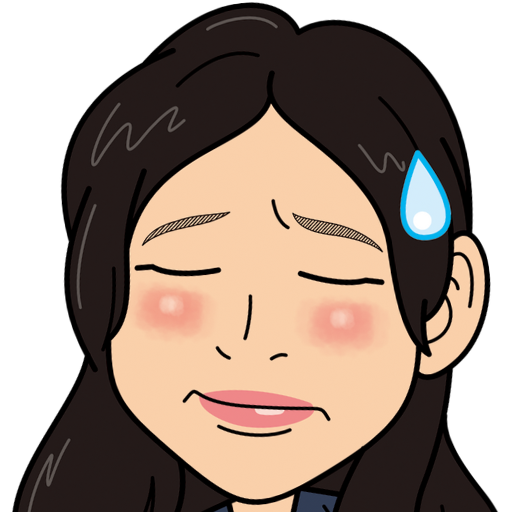
なぜこの法律において法改正が行われたんだっけ・・・?
といった、労働関係諸法令の本質に立ち返る時に参照しています。

法律の基本的な考え方と全体像は『労働法』で確認するとよいでしょう
③各種資料・雑誌
三つ目におすすめしたい勉強ツールは、無料・有料で得られる各種の資料や雑誌です。
JILPTの資料
まずは、JILPT(独立行政法人 労働政策研究・研修機構)の資料です。
JILPTとは、厚生労働省所管の独立行政法人で、労働の実情や労働政策について調査・研究している機関です。
たとえば、2020年1月には「年金保険の労働法政策」についてのレポートが発行されたり、2021年2月には新型コロナウイルスと雇用の関係についての統計データが公表されたりしています。
社労士として、長期的な視点で業務を行なっていくのに役立つ資料が盛りだくさんです。
日常業務で活用するというよりは、国や厚生労働省が向かう方向性を知るときに使うサービスかなと思います。
非営利なので、資料や統計データは無料で公開されています。
株式会社労務行政『労政時報』
つぎは、株式会社労務行政が発行している雑誌『労政時報』です。
WEB版がオススメです。
私は、実務で分からないことがあれば、まず労政時報で検索してみます。
企業や働く人への調査や統計資料もあれば、弁護士や社労士の方々が回答するQ&Aも検索可能です。
料金プランはいくつかありますが、WEB版の年間契約で83,600円(税込)(2023年4月現在)です。
労政時報では、法令・通達・判例・コンメンタールなどを横断的に検索できる「労働法ナビ」が提供されていました。
しかし、2022年2月末に「労働法ナビ」は終了してしまいました。
「労働法ナビ」ほど便利なサービスはなかなかないのですが、これに代わるサービスを2つ紹介します。
産労総合研究所『労務事情』
まずは、産労総合研究所『労務事情』です。

『労務事情』には、実務に役立つQ&Aや裁判例を丁寧に読み解いた記事などが掲載されています。
オンラインで読みたい方には、「労務事情INTERNET with 労働判例」もおすすめです。
『労務事情』だけでなく、裁判例の解説に特化した『労働判例』もオンラインで見ることができます。


自分が欲しいと思う情報だけでなく体系的にまとめられた情報にアクセスすることも大切です
④株式会社日本法令「SJS社労士情報サイト」
おすすめツールの四つ目は、株式会社日本法令の「SJS社労士情報サイト」です。
SJS社労士情報サイトは、主に開業社労士向けのサービスです。
営業支援ツールをダウンロードできたり、PRページに情報を掲載したりすることができます。
ベーシック会員は、年間28,380円(税込)(2023年4月現在)です。
書式や就業規則のひな型をダウンロードでき、ビジネスガイドもオンラインで見ることができます。


SJS社労士情報サイトでは多数の便利なひな型をダウンロードできます
⑤転職サイト「MS Agent」
広く管理部門に関する情報を収集するには転職サイトに登録するのも有用です。
株式会社MS-Japanが運営しているMS Agent(エムエスエージェント)は、社会保険労務士などの士業を含め、経理・財務・人事などに特化した転職サイトです。
株式会社MS-Japanは管理部門人材紹介のトップエージェントで、創業以来29年間で延べ2万人以上の方々の転職のサポートを実現しています。
MS Agentでは、社会保険労務士の資格を持つ人を募集している求人を検索することができます。
求人は4,000件以上掲載されています。
資格保有者の年収相場を知ることも可能です。たとえば東京で検索すると、300万円〜1,000万円とかなり幅があります。
英語力があれば年収が高いことが分かるなど、自分のスキルアップにも役立つ情報が得られます。
また、MS Agentに登録すると同じアカウントで「Manegy(マネジー)」というコミュニティサイトも利用可能です。
Manegyでは、専門家による最新の法令改正レビューや管理部門についてのコラムを読むことができます。
人事労務管理に関するひな型をアップロード・ダウンロードすることもでき、機能が豊富です。
社労士の登録番号を記載してプロフィールを作成すれば、より多くの機能を使えます。
営業ツールにも使えそうですね。
MS Agentに登録することで、Manegyも使うことができます。

社労士には大手転職サイトのほかMS-JapanのMS Agentがおすすめです
社労士試験に確実に合格するための勉強法については、以下の記事をご覧ください。
おすすめ勉強ツール5選のまとめ
- 社労士試験合格後に知識をアップデートするには勉強を続けなくてはならない
- 基本的な法改正は、社労士会の会報やメルマガで情報収集する
- 実務で役立つ情報は、JILPT、労政時報、労務事情、労働判例、SJS社労士情報サイトがおすすめ
- 社労士の市場ニーズの把握や管理部門についての情報収集にはMS Agentがおすすめ