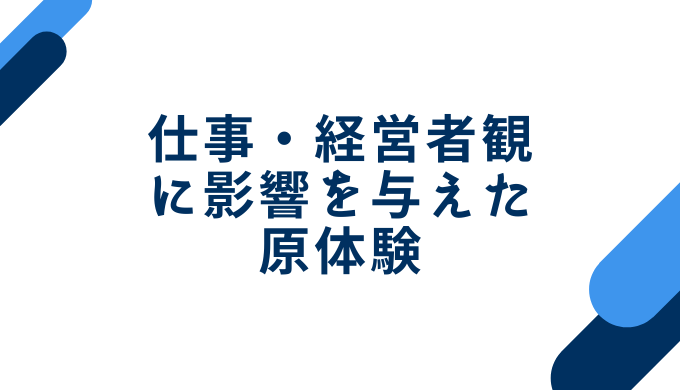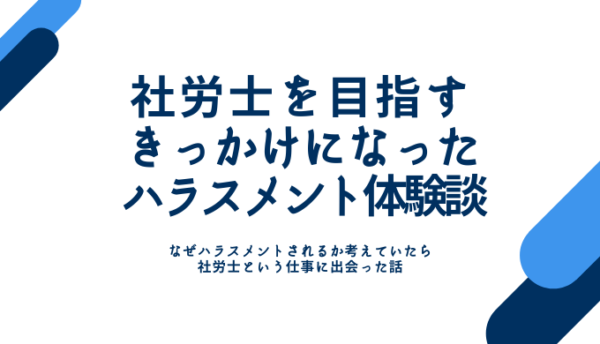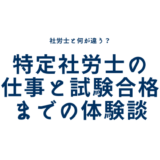社労士のシモデ(@sr_shmd)です。
社労士事務所に勤め始めたのは30歳になる直前のころでした。
そして4年半勤めた後に独立いたしました。
社労士として仕事をするときに大切にしているのは、「お客さまと可能な限り対等な関係を築くこと」と「組織のトップが一番マジメに働くこと」です。
今回は、こうした仕事観・経営者観に影響を与えたシモデの原体験を紹介します。

この記事は次のような人にオススメです!
- シモデのプロフィールを知りたい人
- 幼いときの体験が何に影響を与えるか興味がある人
- 社労士になるにはどんなきっかけがあるのか知りたい人
働く人とお客さまの両方が身近だった幼少期
子どもの頃に友人と話していて、今でも覚えているエピソードがあります。

わたしはお父さんがどんな仕事をしているか知らな〜い
幼心にとても衝撃を受けたのを覚えています。

お父さんが外で働いている人はどんな仕事をしているか知らないこともあるんだ!
なぜ私が「自分の父親がどんな仕事をしているか知らない」という状況に驚いたかというと、私の父は住まいと同じ建物で働いていたからです。
私が育った家は、1階が店舗になっている店舗兼住宅の建物でした。
3歳頃までは住居と同じフロアに従業員の方々の休憩室がありました。休憩中の従業員の方によく可愛がってもらったことも、おぼろげながら覚えています。
また、繁忙期には母が従業員の方々の食事を作っていることもありました。
学校に通うようになると、1階に降りて従業員の方々に「いってきます!」といってから家を出ることが日課になりました。
私にとっては、親がどんな仕事をしていて、どんなお客さまからお金をいただいているのか、知っていることの方が普通だったのです。
基本になった仕事観
祖父や両親からよく言い聞かされていたのは、以下の2つです。
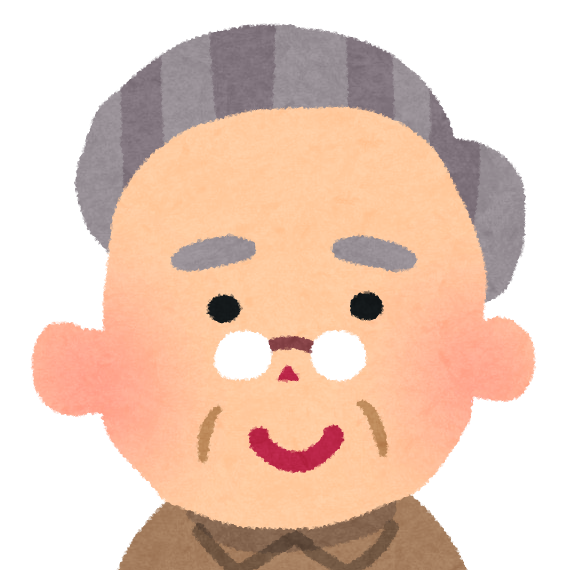
お店は遊び場じゃないから入ってはいけないよ
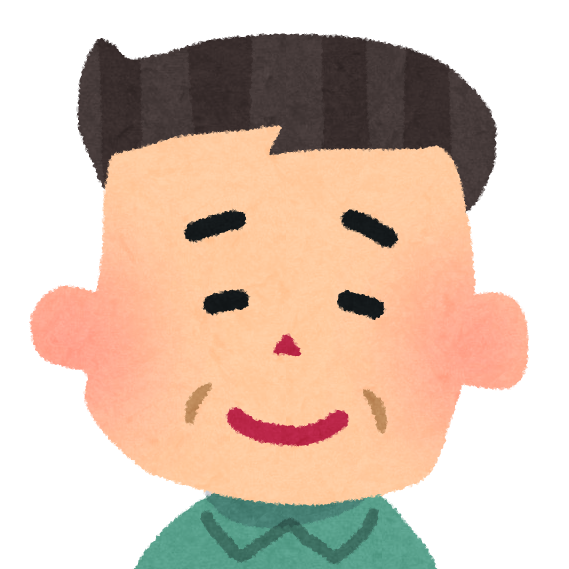
商品は会社のもので自分たちのものではないから勝手に取って行ってはいけないよ
食品を扱っていたため衛生面からもなおさらだったのでしょうが、店舗の空間に許可なく入ったり、そこで遊んだりすることはありませんでした。
また、自分たち家族も会社の商品を買っており、売れ残ったからといってそれを貰ったりすることもありませんでした。
店舗に入ることは滅多になく、商品は自分たちのものでなく会社のものであるという明確な線引きがありました。
一方で、店舗と住居が同じ建物なので、毎日お客さまの顔を目にします。
家族の働く様子とお客さまの様子を毎日目にするうちに

商品を買ってくれる方がいるから自分たち家族が暮らしていけるんだ

家族が作る商品がお客さんたちを喜ばせているんだ
と思うようになりました。
「商品を作ってあげる方が偉い」「お客さまは神様」のどちらでもなく、「作り手がサービスを提供し、価値を感じた方がお金を支払ってサービスを買う」という対等な関係性が私にとって自然な考え方になりました。
基本になった経営者観
経営者は従業員の人生までは拘束できない
お店を始めた祖父は、私が物心ついたときにはすでに現場から退いていましたが、良くも悪くも受けた影響はいくつかあります。
まず、従業員の方々へのスタンスです。
1970年にお店を始め、翌年株式会社にしてからすぐに、従業員の方々を社会保険に加入させました。
現代では法人が社会保険に加入させることは当然のことですが、当時、食品業界の職人の長期的な生活を担保する会社は非常にまれでした。
一方で、多いときには130人くらいの方を雇っていた祖父は、人が辞めるときには「去る追わず」と言っていたそうです。
自分が採用した人が辞めることに対する強がりだったのかもしれません。
しかし、会社のために働いてくれた従業員でも、その人の人生にまで干渉できるものではないのです。
そして、祖父は品のよいものを身に着けることにも拘っている人でした。
職人をしていた祖父ですが、職業人生の後半は人前に出る仕事が多くなっていました。
店舗に置く什器なども非常にこだわりを持ち、東京に輸入品を買い付けに行っていたそうです。
経営者が誰よりも一番マジメに働く
そして父からは、仕事へのスタンスについて影響を受けました。
父は決して器用なタイプではありませんが、毎日毎日マジメに働く人です。
祖父が現場に立たなくなってから店舗の代表は父が担っていましたが、朝の準備から終業後の片付けまで、もちろん父も行います。
従業員の方々からすると、気を使うので代表者はあまり現場に来てほしくないという考え方もあるかもしれません。
しかし、私は(会社の規模にもよりますが)「中小企業の代表者は雑用もするべき」という考え方を持っています。これは、毎日マジメに働く父の姿から影響を受けていると思います。
社労士は中小企業の労務管理のサポートをさせていただく仕事ですが、私の仕事においては上記のような仕事観・経営者観が反映されております。
大人になってから社労士という仕事に出会った話については、以下の記事をご覧ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。