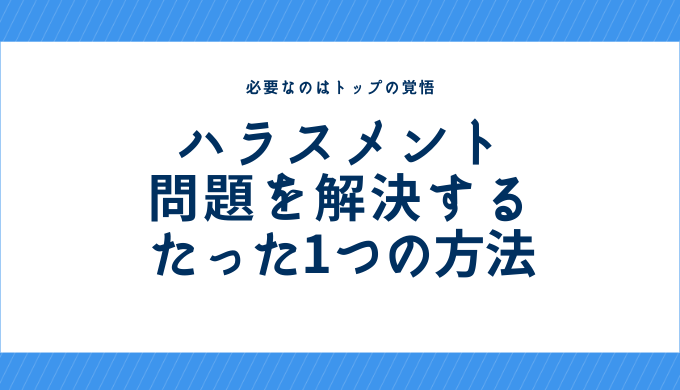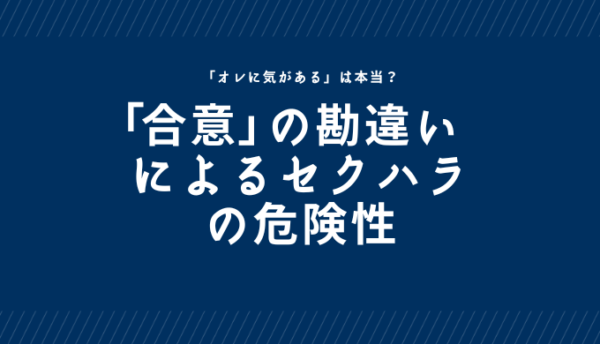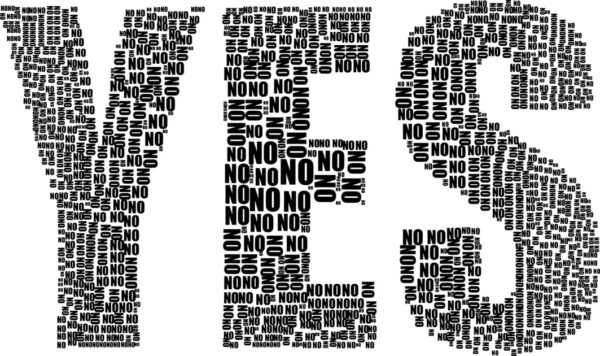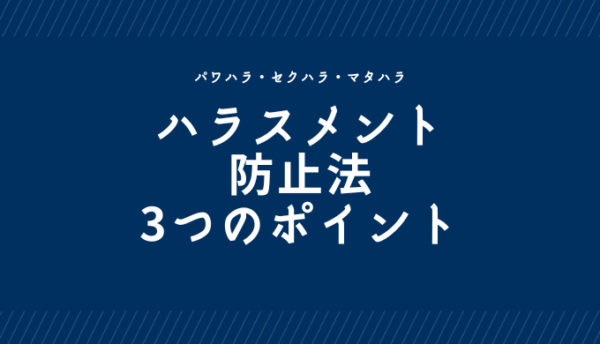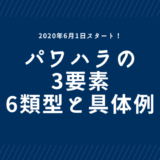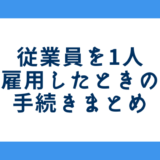社労士のシモデ(@sr_shmd)です。
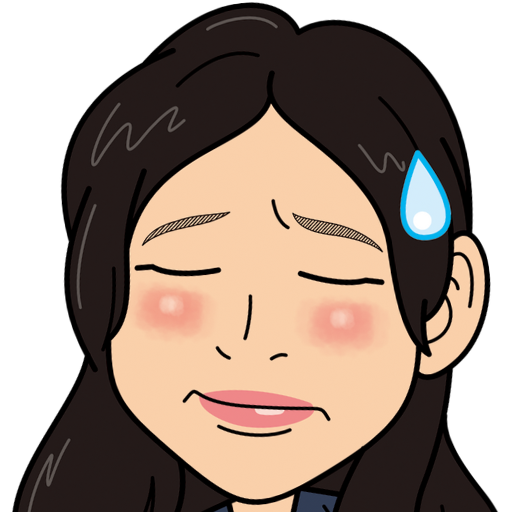
なぜ私はハラスメントを受けたのだろう・・・?
こうした疑問から、私のハラスメント問題への関心が始まりました。
法律や裁判例などを読み、ハラスメント関連の本を読み、男女の違いに関する本や、恋愛に関する本、生物学や進化心理学、社会学に関する本を読んできました。
結果として、問題は複雑だということと、一つだけは確かに言えることがある、ということが分かりました。
それは、「ハラスメント問題の解決にはトップの覚悟が欠かせない」ということです。
そこでこの記事では、ハラスメント問題におけるトップの覚悟の重要性について考えてみたいと思います。

この記事は次のような人にオススメです!
- ハラスメント被害に困っている人
- なぜハラスメント問題が起こるのか知りたい人
- 会社でハラスメント問題の担当をしている人
人間は繁殖成功のために利己的にふるまう?
会社で仕事をしている人たちの中には、大人しかいないはずです。
しかしながら、小さな嫌がらせから暴力まで、ハラスメントは絶えません。
それはつまり、職場においても「ハラスメントをしてはいけない」と、人間は冷静に判断できないということです。
急には環境に適応できない
進化論を唱えたことで有名なダーウィンは、以下のように述べました。
自然は飛躍しない。
チャールズ・ダーウィン『種の起原』
この言葉は、「人間も急には環境に適応できない」ことを示していると私は考えています。
世間でセクハラやパワハラの加害者が糾弾され、社会的な地位を追われるニュースは後を絶えません。
ハラスメントがタブー視される世の中でも、ハラスメント問題はなくならないのです。
その理由は、「ハラスメントをすると社会的地位を失う」という環境に、人間は急には適応できないからだと考えています。
人間が生きる目的は繁殖成功?
また、『利己的な遺伝子』を著したことで有名なリチャード・ドーキンスは、以下のように述べました。
生命の目的は「生存の機会」の最大化である。
リチャード・ドーキンス『利己的な遺伝子』
つまり、人間が生きる第一の目的は、繁殖を成功させて自分の遺伝子を残すことだということです。
したがって、私たち人間が本能的に自分のために生きることや利己的に振る舞うことは当然のことだと思います。
たとえば、女性はセクハラ被害を訴えているのに、男性が「合意の上の恋愛だ」と勘違いするケースがあります。
女性にはその気がなくても男性はポジティブに捉えた方が繁殖成功度が高まるため、勘違いする方に性淘汰が働くと考えられています。
この勘違いは、職場のセクハラ問題のきっかけの一つです。
または、若い女性を年配の女性がいじめるという光景もよく見るものです。
職場という閉ざされた環境の中で、若い女性が好まれる状況に我慢できないのかもしれません。
この嫉妬心が、職場のパワハラ問題のきっかけとなり得ます。
脳は1万年変わらない
進化心理学の本ではよく、以下のように述べられています。
人間の脳は1万年変わっていない。
アラン・S・ミラー他『進化心理学から考えるホモサピエンス』 など
現代の日本社会では、一度には1人しか配偶者を作れないのですから、理論上は女性の反応をポジティブに捉えてセクハラをする必要はありません。
また、若い女性がチヤホヤされているからといって、自分のお給料が下がるわけではないのですから、いじめる必要もありません。
しかし、冷静な判断ができずセクハラやパワハラをしてしまう人がたくさんいます。
自然は飛躍せず、人間の脳は1万年変わらず、生命は利己的にふるまうからです。
匿名社会における協力と対立
職場のハラスメントは、上下関係があるところに起こるケースがほとんどです。
では、あるべきリーダー像は、部下一人ひとりの性質を完璧に理解して、個別に対応することなのでしょうか。
リーダーは部下一人ひとりに対応できるよう努力するべきだとは思いますが、それでハラスメントがなくなるとは思いません。
仕事はチームで行うもので、リーダーが部下に対して個別に対応したとしても、諍いはなくならないと思うからです。
知らない人とも仕事はできる
人間は、協力もするし対立もする生き物です。
その理由の一つは、人間社会が「匿名社会」だからです。
名前も年齢も何も知らない人とも、同じ社会を作っていくことができます。
これは人間とアリのみに見られる特徴だそうです。
考えてみれば、素性の知れない人たちと同じ電車で移動したり同じカフェで休憩したりできる生き物は、とても稀なのでしょう。
職場でも、年齢や誕生日など、相手のことをほとんど知らなくても一緒に仕事をすることができます。
部下の名前を覚えていない上司も、世の中にはたくさんいるのではないでしょうか。
隣に座っている人が何の仕事をしているか知らなくても、業務は回っていきます。
ささいな違いが協力にも対立にも繋がる
匿名社会では、ささいな違いがアイデンティティの形成に重要な意味を持ちます。
「ささいな違い」とは、以下のようなものです。
- いでたち
- 服装
- 髪型
- 表情
このような「ささいな違い」がアイデンティティを示すのは、大量に知らない人が集まっている中で仲間かそうでないかを瞬時に見分ける必要があるからです。
ささいな違いにより見分けた仲間同士は協力し合います。
一方で、ささいな違いは異なる集団と対立するきっかけにもなります。
ささいな違いを瞬時に見分ける能力は偏見を生むからです。
自然界においては、異なる病原体を持つ個体との接触から身を守るためには、仲間かどうかを瞬時に判断する必要があります。
自分や子孫、自分が所属する社会を守ることを優先すれば、多少の認識違いは致し方ありません。
人間も生き物である以上、偏見を持たないことは不可能だと思います。
偏見を持たない・無くすことを目指すのではなく、自分がどんな偏見を持っているかを知り、どうコントロールするかを身につけようと努力するものなのだと思います。
「ハラスメントをなくす」ことは不可能?
法律においては、会社に対して、職場でハラスメント問題が起きないよう必要な措置を講じることが義務づけられています。
つまり、会社が講じる措置の目的は、ハラスメントが起きないようにすることです。
はたして、ハラスメントが起きないようにすることは可能なのでしょうか。
「NOを言わない=合意」ではない
職場には上下関係があります。
部下は上司に対して社交辞令を言ったりご機嫌取りをしたりすることがあるでしょう。
これが女性部下から男性上司に対してだと、男性は女性の笑顔を必要以上にポジティブに捉えます。
女性の笑顔を必要以上にポジティブに受け取ると「オレに気がある」という勘違いになり、セクハラに繋がる危険性があります。
確かに女性も最初は上司を尊敬していたというパターンもあるでしょう。尊敬と恋愛の感情は似たものです。
ハラスメント被害を受けたときにはっきりと拒否できれば良いのですが、被害者にとっては簡単なことではありません。
裁判例の積み重ねによって、ハラスメント被害を受けたものはキッパリと拒絶できない心理状態になるということが分かってきています。
「合意の上の恋愛だった」という説明は通用しないのです。
ハラスメント研修は意味がない?
では、ハラスメント問題が起きないようにするためには、教育をすればよいのでしょうか。
会社でハラスメント研修を行うことは法的に求められており、ハラスメント対策をしているという従業員へのアピールにもなります。
しかしながら、研修を行うとそれが「免罪符」となり、むしろハラスメントを増長させてしまうという研究結果もあります。
これは、「道徳の貯金」理論で説明できると思います。
「道徳の貯金」理論においては
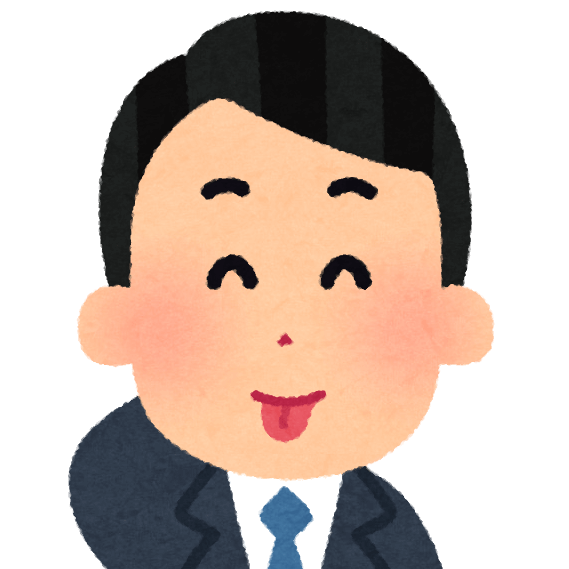
今日は真面目にハラスメント研修を受けたから、少しくらいハラスメントをしても冗談として受け入れられるだろう
と、悪いことをしても蓄えておいた道徳的なことで相殺できると考えてしまいます。
どれほどリソースを割けるか
では、ハラスメント問題が起きないようにするためには、従業員にアンケート調査をすればよいでしょうか。
これについては教育や研修とは異なり、ハラスメントを増長させるといった「反対の効果をもたらす」と述べられた文献はまだ見かけていません。
職場の全体的な傾向をつかむには、一定の効果があると思います。
ただ、従業員全員が本音を書けるわけではないでしょう。
また、研修もアンケート調査も、会社に余力があればこそできることです。
もともと関心がある会社は実施するでしょうし、ハラスメント体質のある会社は見向きもしないでしょう。
このように、人間の特性や現場の意見から、「ハラスメントをなくす」という目標を掲げるのは現実的ではないのではないかと考えるようになりました。

「ハラスメントをなくす」という理想を持っておく一方で、現実的な解決策を持つことが大切だと考えます
トップが覚悟すれば適切な対応ができる
ハラスメント防止措置の義務づけ
2020年6月1日に「労働施策総合推進法」が施行され、会社ではセクハラ・マタハラ・パワハラを含むハラスメント防止措置を講じることが義務づけられました(中小企業では、パワハラに関しては2022年4月1日より義務化)。
会社に義務づけられているハラスメント防止措置は、主に以下の3つです。
- ハラスメントを行ってはならないという会社の方針を明らかにして、それを周知・啓発すること
- ハラスメントに関する相談や苦情に適切に対応するための体制を整えること
- ハラスメント問題が発生したら、速やかに適切に対応すること
会社ではハラスメントを防止するために、方針を就業規則に記載して周知・啓発すること、相談窓口を設置して相談があれば適切に対応することが必要です。
「適切な対応」とは?
ハラスメント防止措置がいうところの「適切な対応」とは何でしょうか。
実際にハラスメント問題が発生したとき、加害者が役職者であるなど、仕事ができたり重要なポストについたりしている場合は会社が加害者の処分に困ってしまうことがあります。

ハラスメント加害者を異動させたら業務が回らなくなる・・・
と、ハラスメント問題を解決することから目を逸らしてしまいそうになるのです。
ハラスメント問題の多くは、上下関係のもとに起こります。
多くは上の立場の者が加害者、下の立場の者が被害者となります。
ときには、役員が加害者になることもあります。
社長さんや人事権を持つ役職者から見ると、被害者よりも加害者の方が付き合いが長かったり、加害者の方が成果を出していて優秀だと評価されていたりすることも多いでしょう。
加害者か被害者のどちらかを異動させたり辞めさせたりしなければいけないとき、被害者を対象にしたい気持ちがわくかもしれません。
加害者を処分することを覚悟しておく
しかし他の従業員たちは、社長などトップの方がどのように対処するかを注意深く見ています。
社長さんは、ハラスメント問題への対処が周囲にどのような影響を与えるのかということを含め、組織全体のことを考えて決断しなければならないのです。
したがって、ハラスメント問題が起きたときに本当に必要になる「適切な対応」とは、ハラスメント行為が認定されたら加害者をしっかりと処分することに尽きると考えます。
そのため社長さんは、加害者がどれほど優秀であっても「加害者を処分するのだ」という覚悟を持たなければなりません。
ハラスメントに対する会社としての正式な処分には、異動と懲戒が挙げられます。
特に懲戒は守らなければならないルールがたくさんあります。
懲戒処分を科すには、必ず問題が発生する前に就業規則にルールを定めておかなければなりません。
就業規則と懲戒制度については、以下の2つの記事も参考にしてください。
社長さんは日々さまざまな決断をしていることと思います。
特に相手が人であるときには決断が難しいことでしょう。
しかし、いくら優秀であっても「加害者を処分するのだ」と覚悟しておくことが、ハラスメント問題の解決に必須なのです。
<参考資料>
- アラン・S・ミラー他『進化心理学から考えるホモサピエンス』(2019) パンローリング株式会社
- イリス・ボネット『WORK DESIGN 行動経済学でジェンダー格差を克服する』(2018)NTT出版
- ウィリアム・フォン・ヒッペル『われわれはなぜ嘘つきで自信過剰でお人好しなのか』(2019)株式会社ハーパーコリンズジャパン
- 越智啓太『恋愛の科学 出会いと別れをめぐる心理学』(2015)実務教育出版
- ジェニファー・エバーハート『無意識のバイアス 人はなぜ人種差別をするのか』(2021)明石書店
- チャールズ・ダーウィン『種の起原』(1990) 岩波文庫
- マーク・W・モフェット『人はなぜ憎しみあうのか』(2020)早川書房
- 牟田和恵『部長、その恋愛はセクハラです!』(2013)集英社新書
- 山下淳一郎『ドラッカーが教える最強の後継者の育て方』(2020)同友館
- 尹雄大『さよなら、男社会』(2020)亜紀書房
- リチャード・ドーキンス『利己的な遺伝子 40周年記念版』(2018) 紀伊國屋書店
- ロバート・トリヴァース『生物の社会進化』(1991)産業図書