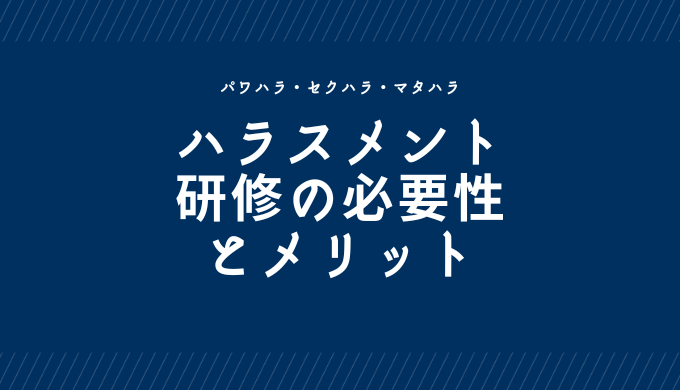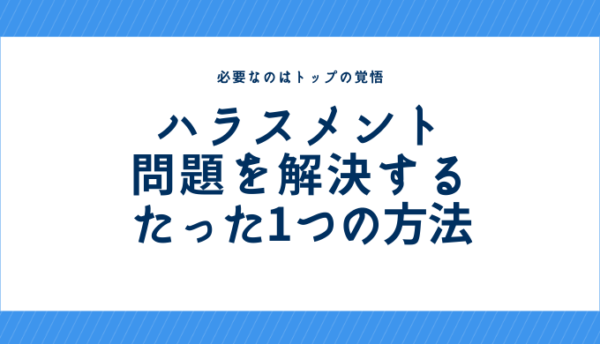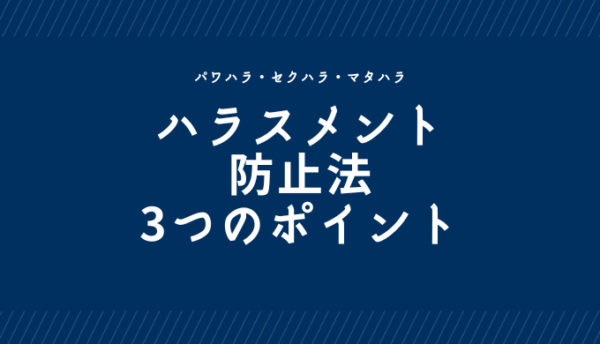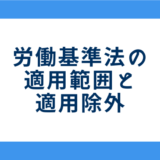社労士のシモデ(@sr_shmd)です。

授業がつまらないなあ〜〜〜
子どものころ、こんなふうに感じたことは誰しもあると思います。
面白くない話を聞き続けることは辛いものです。
大人になってもそれは同じではないでしょうか?
ハラスメント問題においては、法律の内容や定義、裁判例などを知っておくことは大切です。
しかし、本当に聞いて欲しい人に響いているのか疑問に思うことがあります。
この記事では、ハラスメント研修の必要性とメリットについて考えてみたいと思います。

この記事は次のような人にオススメです!
- ハラスメント研修の必要性に疑問を持つ人
- ハラスメント研修の実施を任されている人
- ハラスメント対策を担当している人
ハラスメント研修の必要性
研修を行うことは会社の責務
ハラスメント研修は、以下のように、法律では会社の努力義務として定められています。(労働施策総合推進法第30条の3、男女雇用機会均等法第11条の2、育児介護休業法第25条の2)
- ハラスメントについての従業員の関心・理解を深めたり、自分の言動に十分注意を払ったりするように、研修の実施その他の必要な配慮をする
- 経営者や役員自らも、ハラスメントについての関心・理解を深めて、従業員に対する言動に十分注意を払う
またハラスメントを防止するため、会社には次の3つの措置を講じることが義務づけられています。(労働施策総合推進法第30条の2、男女雇用機会均等法第11条、育児介護休業法第25条)
- セクハラやパワハラを行ってはならないという会社の方針を明らかにして、それを周知・啓発すること
- セクハラやパワハラに関する相談や苦情に適切に対応するための体制を整えること
- セクハラやパワハラ問題が発生したら、速やかに適切に対応すること
1の措置の具体例として、就業規則の整備のほか、ハラスメント防止を周知・啓発するための研修や講習を行うことが挙げられています。

法的にはハラスメント研修は必要といえます
会社が指定する研修はやる気がでない?
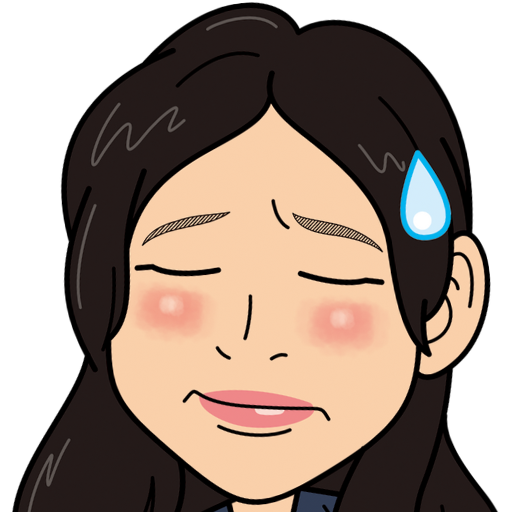
あの人、研修の話を聞いていないな・・・
ハラスメント研修をしていると、話を聞いていない方、居眠りをしている方が必ずいらっしゃいます。
それもそのはずです。
ハラスメント研修が会社の責務であるということは、従業員は研修を受けることを強制されるということだからです。
好奇心旺盛な方であったとしても、知識を身につけるよう強制されるのは楽しいものではないと思います。
ハラスメント研修の有効性への疑問
法律で義務づけられているからという理由でハラスメント研修を実施する会社が多いのではないでしょうか。

研修を実施したらハラスメント問題がなくなりました!
これほど単純に解決できれば、誰も苦労しません。
研修の実施は職場の多様性に影響を与えない
ハラスメント防止に対する研修の有効性への疑問の答えとなる一つの研究結果があります。
ハーバード大学によるアメリカの800社超の中小企業と大企業を対象とした1971年から2002年の30年以上にわたる調査です。
調査内容は、多様性の研修と職場の多様性の相関関係でした(この調査では多様性をさまざまな性別・人種・年齢・価値観の人を受け入れることと定義しています)。
調査の結果は
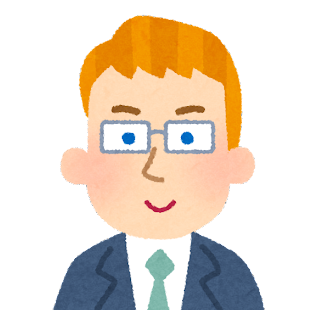
多様性の研修と職場の多様性に直接の関連性はありません
というものでした。
理由となる一つの仮説があります。それは、多様な人を受け入れることは非常に難しいということです。
多様性を受け入れるには、少なくとも次の4つのステップがあると言われています。
- 自分の考えが偏見の影響を受けている可能性を認識すること
- 偏見がどのように働くか理解すること
- 自分が偏見におちいったときに、それをすぐに認識すること
- フィードバックや分析、コーチングを頻繁に受けること
この4つを繰り返して身につけていくことはとても難しいことです。
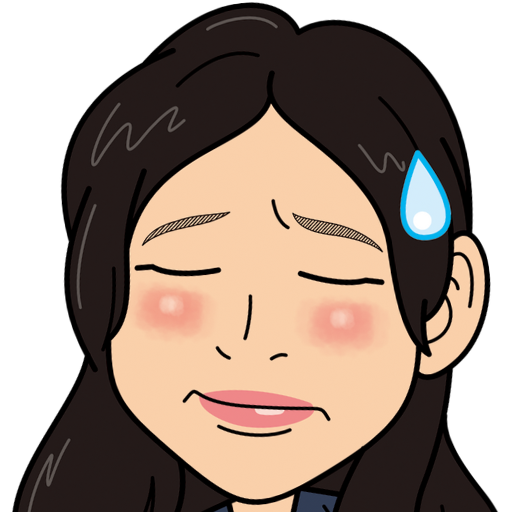
ハラスメント問題は思い込みや偏見をきっかけに起こります。研究結果を踏まえると、ハラスメント研修と職場の多様性・受容性は無関係なのかもしれません
ハラスメント研修のメリット・デメリット
法的義務の履行・従業員へのアピールができる
ハラスメント研修が職場の多様性や受容性と無関係なのだとしたら、ハラスメント研修を実施するメリットはあるのでしょうか。
ハラスメント研修には、以下2つのメリットがあると考えます。
- 法的な義務を果たすことができる
- 従業員へのアピールになる
ハラスメント研修を実施するメリットの一つ目は、会社の責務を果たせることです。
法律としては努力義務ではありますが、ハラスメント防止措置義務の具体例に研修の実施が挙げられています。
そのため、法律を遵守しているという社会的な責任を果たすことができるのです。
二つ目のメリットは、従業員へのアピールになることです。
ハラスメント研修を実施することで、ハラスメントに問題意識を持っていることや対策をしようとしていることを従業員に伝えることができます。
採用においても応募者に対するアピールになるかもしれません。

ハラスメント研修には法的義務の履行・従業員へのアピールという2つのメリットがあります
研修が免罪符になる!?
しかしながら、ハラスメント研修にはデメリットもあります。
それは、研修の実施が逆効果になることもあることです。
なぜなら、人間は好ましい行動を取ったあとに悪い行動を取る傾向があると言われているからです。
この傾向を裏付ける事例として、2008年のアメリカ大統領選でオバマ氏への支持をあらわす機会のあった人は、その後、アフリカ系アメリカ人を差別する確率が高まったという実験があるそうです。
身近な例でいうと、ダイエット中の人が

今日は仕事を頑張ったからケーキを食べちゃおう
と、仕事を頑張ったという好ましい行動のあとに、ダイエット中にもかかわらずケーキを食べるという悪い行動を取ることはよくあるのではないでしょうか。
ハラスメント問題について当てはめると、研修を受けるという好ましい行動を取ったあとは、逆にハラスメントをしてしまう可能性があるということです。
『WORK DESIGN』の著者は、次のように述べています。
職場でとりわけ悪質な差別をおこなっている人の行動を是正するために、多様性についての研修を受けさせると、完全に逆効果になる危険があるのかもしれない。
差別的なマネージャーが多様性についての研修を受けると、それにより自分が「免罪符」を得たと感じ、差別的な態度を取ってもかまわないと思いかねないのだ。
差別に関する研修を受けることにより、かえって性別間や人種間の違いが目につきやすくなる可能性も考えられる。(略)
以上の点を考えると、多様性についての研修には効果がないと結論づけざるをえない。少なくとも、どのような条件下で効果があるかを判断できるだけのデータはない。
イリス・ボネット『WORK DESIGN 行動経済学でジェンダー格差を克服する』
実際、ハラスメント研修を行った会社さんにおいて、その研修を実施した担当者の方がセクハラにより辞めたという話を聞いたことがあります。
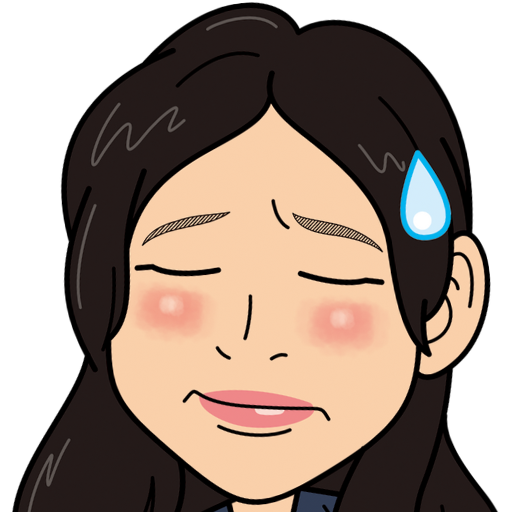
ハラスメント研修のあとはむしろハラスメントが増える可能性があることを頭に入れておきましょう
有効なのは「社長のメッセージ」と「罰」
とはいえ会社は従業員に対して、ハラスメントに関する何らかの情報提供や教育、研修は行っておくべきです。
ハラスメント被害を訴えた従業員が「会社にも責任がある」と主張したときには、会社が教育の機会を与えていたかについての法的責任を問われる可能性があるからです。
ただ、ハラスメントをなくすために、研修が有効であるかどうかは疑問です。
なぜなら、ハラスメント研修は「人の良心に訴えかけるもの」だからです。
ハラスメント行為をしてしまう人の良心に訴えてものれんに腕押しで、効果はないかもしれません。
研修の実施に加えて、ハラスメントをさせないために重要なのは以下の2つだと考えます。
- 会社のトップが「ハラスメント行為をした従業員をどう処分するか」を周知しておく
- 実際にハラスメント行為が認められたら決めた通りに処分をする
処分の内容が明確でなければ、ハラスメント行為をしてしまう人に自分の行動を反省させることができません。
実際に処分を行わなければ「悪いことをしてもキャリアに影響はないんだ」という雰囲気が、行為者だけでなく会社全体にも広がってしまいます。
ハラスメント問題における会社のトップによるメッセージの重要性については、以下の記事もご覧ください。
また、会社の罰として従業員に対し「懲戒処分」を行うためには、あらかじめ就業規則に定めておく必要があります。
問題が起こってから就業規則を変更しても、その事案に対しては懲戒処分を行えません。
懲戒制度については、以下の記事をご覧ください。
一方、ハラスメントの被害にあっているかたは、以下の記事に相談の基本的なフローをまとめておりますので参考にしてみてください。
社内で相談できる人を探す、会社の相談窓口に相談することが原則的な初動になりますが、社内で相談することはハードルが高いと感じたら、利害関係のない社労士に相談することも一つです。
直接あなたを救うことはできなくても、一緒にお気持ちを整理してどのような第一歩を踏み出すかを考えます。
セクハラ・パワハラの解決方法を一緒に考えます 現状とお気持ちを整理して、第一歩を踏み出すお手伝いをしますハラスメント研修の必要性とメリットのまとめ
- ハラスメント研修を行うことは会社の責務として必要
- ハラスメント研修を行うメリットは、法的義務を果たせることと従業員にアピールができること
- しかし、ハラスメント研修を受けたことが「免罪符」となり、研修実施後はハラスメント事案が増える可能性がある
- ハラスメント研修の実施に加えて、社長やトップが「ハラスメント行為をした従業員をどう処分するか」を周知しておき、実際にハラスメント行為が認められたら決めた通りに処分をすることが重要