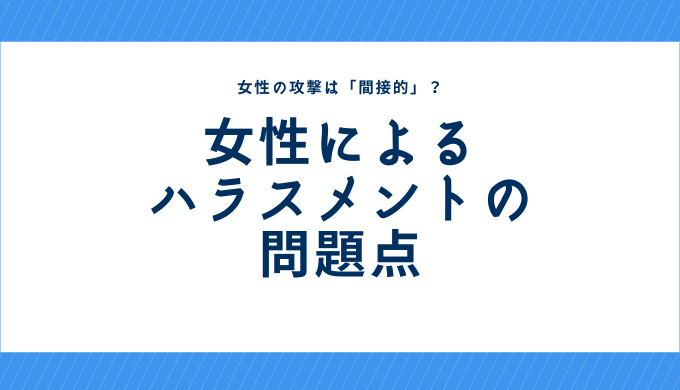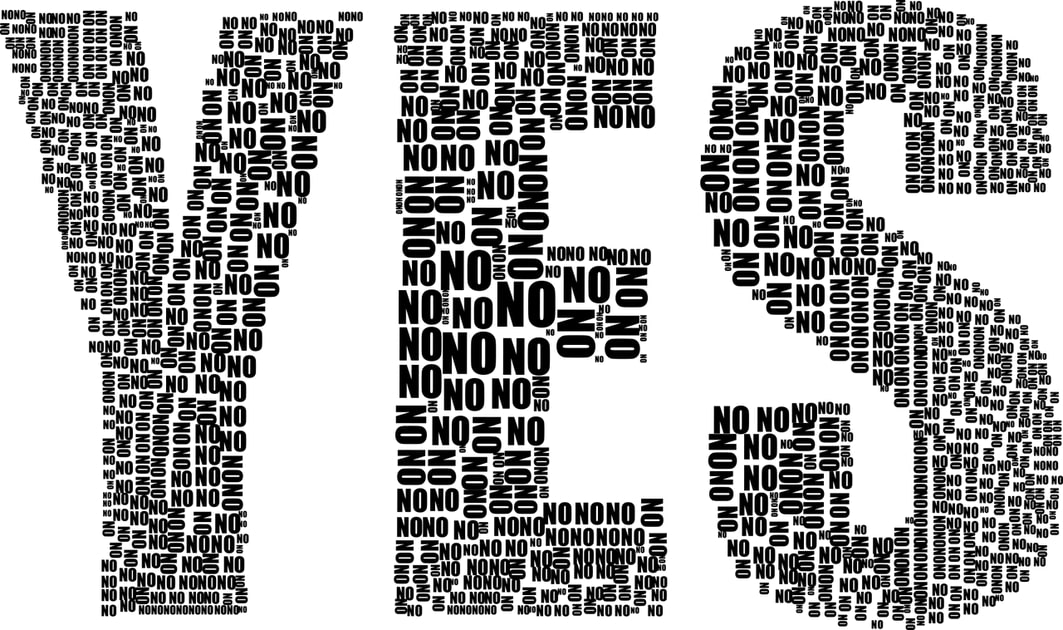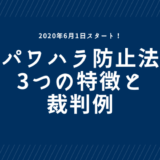社労士のシモデ(@sr_shmd)です。
パワハラやセクハラで裁判に至るような事例では、加害者となるのは圧倒的に女性より男性の方が多いです。
裁判においては、加害の程度が大きく、被害者が精神疾患を発症したり自殺してしまったりした事案が争われます。
一方で、職場で日常的に問題になるのは、加害の程度がもっと小さいハラスメントです。
とくに加害者が女性であるケースは、裁判にまで至る事例が多くはありません。
一見、女性によるハラスメントの数が少ないように思えます。
しかしながら、友人や知人に問いかけてみると、女性にパワハラやセクハラをされたとよく聞きます。
そこでこの記事では、女性によるハラスメントの問題点について考えてみたいと思います。

この記事は次のような人にオススメです!
- 女性によるハラスメント被害に困っている人
- 女性によるハラスメントから身を守る手段を知りたい人
- 女性が多い職場で管理職をしている人
女性によるハラスメントの特徴は?
力が弱い者の攻撃戦略
男性と女性の攻撃の戦略は、身体的な特徴によって変わってくると考えられています。
男性と女性の体は、筋肉量が違います。
基礎代謝量の男女比は5:4です。
70歳以上の男性の平均1,290(kcal/日)と15〜17歳の女性の平均1,310(kcal/日)に、それほど差はありません。
このように力が弱い女性は、どのような攻撃戦略をとるのでしょうか。
女性の攻撃は間接的で見つかりにくい
進化心理学者のアン・キャンベルによると、女性は子どものために長く生き残ることが何よりも重要であるため、女性たちがとる戦略はリスクが低く「間接的なもの」だといいます。
間接的な戦略においては、例えば、盗みであれば強奪ではなく窃盗を選びます。
ライバルを出し抜くには、暴力で直接対決するのではなく、影で悪い噂を広めます。
間接的な攻撃は、直接的な攻撃よりも周囲からは見つかりにくいでしょう。
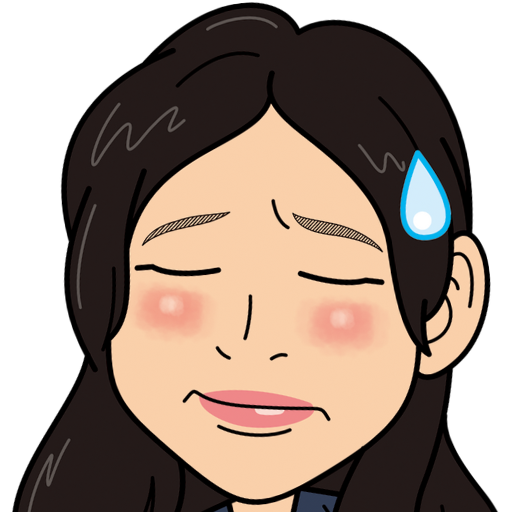
女性によるハラスメントは見えにくい分注意が必要です
女性加害者に対しても当然に注意・指導が必要
離職者が多ければ要注意

お局さんたちには指導を任せているし、女性同士の争いごとには関わりにくいなあ・・・
こんなふうに問題を放置していて本当によいのでしょうか。
女性によるハラスメントは、「ない」のではなく「見えにくい」だけなのかもしれません。
勤続年数の長い女性がいる職場で若者の離職者が多ければ要注意です。
パワハラやセクハラがないか、しっかりと観察する必要があると考えます。
被害を訴えられないケースが危ない
女性によるハラスメントの多くは加害の程度が小さく見えにくいので、大きな事案に発展することが少ないのではないかと思います。
男性が女性からハラスメントを受けている場合は、とくに被害の声は届きにくいでしょう。
ハラスメント問題の怖いところは、「相談がないからハラスメントがない」わけではないところです。
退職することを決めた人がいきなり裁判を起こすかもしれません。
管理職の方々は、職場の環境を注意深く観察して必要に応じて調査し、加害者が女性であっても当然、注意・指導や教育、処分を行うべきです。

ハラスメントに関する処分の程度は、加害者が男性であるか女性であるかに関わりありません
なお、ハラスメントの加害者に対して懲戒処分を科す場合には、あらかじめ就業規則にルールを定めておくことが必要です。
懲戒制度については、以下の記事を参考にしてください。
女性加害者の裁判例
2020年2月、神戸市における男性教師への暴行事件の加害者4名のうち1名が女性であることが話題となりました。
12月にもNTTドコモの元社員が、男性上司と女性上司からパワハラ・セクハラをされたとして裁判を起こしています。
数が少ないのは確かですが、女性がパワハラ・セクハラの行為者とされ争われた裁判例はありますので、紹介します。
精神疾患が労働災害と認められた例
女性同士の事例。同僚の女性数名から悪口や陰口、殴る蹴るのマネをされるなど繰り返し嫌がらせをされたことにより、被害者は精神疾患を発症した。陰湿さと執拗さが常軌を逸した悪質なものと判断され、その精神疾患は労働災害だと認定された。
京都下労働基準監督署長事件(大阪地判 平22.6.23)
精神的損害に対する損害賠償請求が認められた例
女性同士の事例。有期雇用の契約社員が正社員3名から占い師のコスチュームを着て研修会に参加するよう強要され、その様子を写した写真をスライドに投影された。被害者は研修会の直後にクリニックへの通院を開始。精神的損害に対して22万円の損害賠償請求が認められた。
カネボウ化粧品販売事件(大分地判 平25.2.20)
会社の管理責任が問われた例
女性加害者、男性被害者の事例。周囲から見ても被害者の仕事ぶりは叱責されても仕方ないという側面もあったが、加害者の叱責は過去のことを持ち出したり、詰問口調であったりした。周囲はどちらかを異動させるよう管理者に訴えたが聞き入れられず、結局被害者は精神障害を発症し自殺してしまった。法人に対し、数千万円の逸失利益と慰謝料を支払うよう命じられた。
社会福祉法人備前市社会福祉事業団事件(岡山地判 平26.4.23)
女性によるセクハラの有無が争われた例
男性へのセクハラ行為者として女性が訴えられた事例。郵便局内浴室で男性が上半身裸の状態でいたところ、女性に近づかれ、じろじろと見られたと主張。一審ではセクハラ行為と認められた。控訴審では、女性は管理職の職務として防犯パトロールのために浴室の扉を開けたこと、細かい会話や言動については両者の主張が著しく異なっており、被害者の主張を採用できないとして、行為の違法性が否定された。
日本郵政公社(近畿郵便局)事件(大阪高判 平17.6.7)
女性によるハラスメントの問題点のまとめ
- 女性は、例えば暴力をふるうのではなく悪い噂を広めるという、リスクが低く間接的な戦略をとる
- 女性によるハラスメントは、「ない」のではなく「見えにくい」可能性がある
- 被害が訴えられないからといってハラスメントがないとは限らない。注意深く観察して必要に応じて調査し、加害者が女性であっても当然に、注意・指導や教育、処分を行うべき
<参考資料>
- 厚生労働省e-ヘルスネット「加齢とエネルギー代謝」
- アラン・S・ミラー、サトシ・カナザワ『進化心理学から考えるホモサピエンス』(2019)パンローリング株式会社
- ロバート・トリヴァース『生物の社会進化』(1991)産業図書